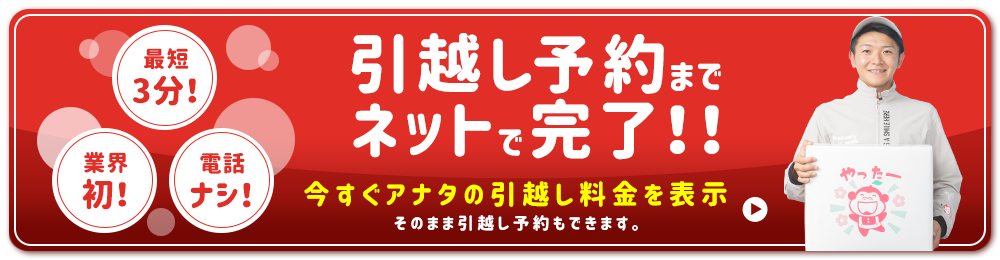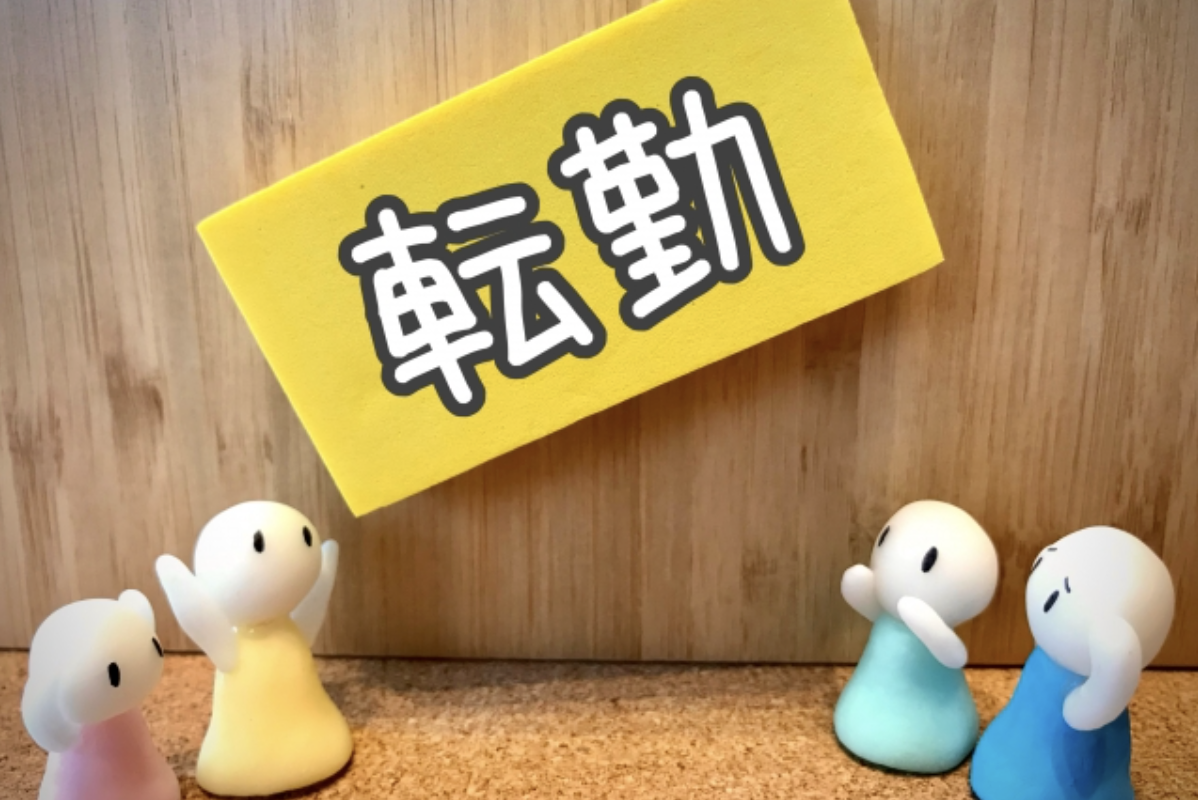【最新】引越しのやることチェックリスト 必要書類から荷造り・引越し後までの流れを徹底解説

このページの目次
必要書類から荷造り・引越し後までの流れを徹底解説します
1ヶ月前から引越し後までのチェックリストを網羅的に解説
そんなときに役立つのが「引越しチェックリスト」です。
事前にリストを作成しておけば、必要な手続きを忘れずに済ませられるだけでなく、効率的に準備を進められます。
この記事では、1ヶ月前から引越し後までのチェックリストを網羅的に解説します。
手続きの漏れを防ぎ、スムーズに引越しを進めたい方はぜひ最後までご覧ください。
まずは、チェックリストを作ることで「するべきことが明確になる」理由について見ていきましょう。
引越し前にチェックリストを用意しておく3つのメリット
1.するべきことが明確になる
2.大きな引越しトラブルが防げる
3.コスト(時間・お金)を節約できる
ひとつずつ見ていきましょう。
メリット1.するべきことが明確になる
●荷造り
●役所での手続き
●ライフラインの契約変更 など
これらを頭だけで管理することは大変ですが、チェックリストを作成すればOK。これらのタスクが明確になり、一目で全体の流れを把握できます。
また、やるべきことの優先順位をつけるのにも役立ちます。
例えば、賃貸契約の解約や引越し業者の予約は早めに済ませる必要がありますが、荷造りは直前でも対応可能です。
このように、チェックリストを使えば、引越しの時間や費用を節約できます。
さらに、リストを見ながら進めることで、手続きの抜け漏れを防ぐことができます。
メリット2.大きな引越しトラブルが防げる
例えば、引越し業者との契約内容(料金やサービス内容)をリストに記載し、事前に確認しておけば、追加料金の発生などのトラブルを防げるでしょう。
また、壊れやすい荷物や貴重品の管理方法を決めておけば、破損・紛失のリスクも低減できます。
さらに、新居の設備や傷のチェック項目をリスト化しておけば、引越し後のトラブル防止にもつながるのです。
不備を見つけたらすぐに管理会社や大家に報告できるので、スムーズに対応できます。
メリット3.コスト(時間・お金)を節約できる
なぜなら、新居で必要なものを事前にリストアップしておけば、余計な買い物を防げるからです。
引越しを機に断捨離をする人もいますが、必要なものまで捨てると、買い直しで費用がかかることもあります。
特に、家具や家電はサイズが合わず買い直すケースもあるため、リストを作成して慎重に選ぶことが大切です。
次の項目からは、アップル引越センターがおすすめする引越しチェックリストを個別に解説します。
引越し1ヶ月前にすること【チェックリスト6項目】
余裕を持って取り掛かりましょう
1.学校への連絡
2.固定電話の移設
3.NHKの住所変更
4.インターネット・衛星テレビなどの契約会社の手続き変更
5.梱包用品の準備
6.不用品・粗大ごみの処分
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 学校への連絡
公立の小中学校の場合、まず在学中の学校で転校手続きを行い、その後、現在の役所で「転出届」を提出します。
新住所の役所で「転入届」を出し、転校先の学校で最終手続きを進めましょう。
必要な書類や手続きは学校ごとに異なるため、早めに確認しましょう。
また、私立の学校や保育園の場合は、空き状況や入園・入学手続きに時間がかかることも。
できるだけ早めの対応を心がけましょう。
2. 固定電話の移設
NTTの場合は「116」へ電話するか、インターネットで手続きを行えます。
< その他の通信会社を利用している場合は、契約先のカスタマーサポートに連絡し、移設手続きを確認しましょう。
繁忙期(3~4月)は手続きが混み合うため、遅くとも2週間前までには申し込みを済ませておくのが理想です。
新居で開通工事が必要な場合は、スケジュール調整が必要になるため、早めに手配しましょう。
3. NHKの住所変更
NHKの公式サイトや電話で手続きを行い、新住所の情報を登録しましょう。
住所変更をしないと、旧住所に請求書が届き続けることがあります。
4. インターネット・衛星テレビなどの契約会社の手続き変更
衛星放送を契約している場合、新居での視聴環境が変わることもあるため、引越し前に確認しておくと安心です。
特に、ケーブルテレビや光回線を利用している場合は、契約内容の変更や追加工事が必要になるケースもあります。
移設工事が必要になる場合もあるため、引越しの1ヶ月前には契約会社に連絡し、手続きを進めましょう。
特に光回線は、開通工事に時間がかかることがあり、引越し後すぐにネット環境を整えたい場合は早めの対応が必須です。
契約会社によっては移設手続きに費用がかかる場合もあるので、事前に確認しましょう。
また、衛星テレビ(BS・CS)やケーブルテレビを利用している場合、新居での受信環境を確認し、必要に応じて契約変更や解約手続きを行います。
契約エリア外の場合、解約が必要になることもあるので注意しましょう。
5. 梱包用品の準備
最低限必要なものとして、以下のものは事前に準備しておきましょう。
●ダンボール
●ガムテープ
●緩衝材(新聞紙やプチプチ)
●油性マーカー
●カッター
●軍手 など
ただし、引越し業者によっては、ダンボールや梱包資材を提供してくれるところもあるので、事前に聞いておくのがおすすめです。
契約時に確認し、足りない場合はホームセンターやネット通販で購入しましょう。
荷造りは、使わないものから順番に進めるとスムーズです。まずは季節外の衣類や本、食器類などから始めましょう。
ダンボールには中身と搬入場所をペンで明記しておくと、新居での荷解きがスムーズになります。
6. 不用品・粗大ごみの処分
不用品の処分方法としては、おもに以下の3つがあります。
●自治体の粗大ごみ回収
●リサイクルショップでの買取
●フリマアプリでの販売
粗大ごみは自治体ごとに回収日が決まっており、予約制のケースも多いため、早めに申し込む必要があります。
また、家電リサイクル法の対象品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)を処分する場合は、リサイクル料金がかかるので注意しましょう。
まだまだ使える家具・家電は、知人に譲ったり、リサイクルショップで売ったりするとお得です。
新居に持っていくものを減らし、引越し費用を抑えながら、快適に暮らせる準備を進めましょう。
引越し2週間前にやること【チェックリスト8項目】
自治体から生活インフラ、保険手続きまで
1.転出届の提出
2.国民健康保険の手続き
3.印鑑登録の廃止
4.児童手当・各種医療制度の手続き
5.火災保険・地震保険の契約住所変更
6.携帯電話の住所変更
7.新聞の住所変更
8.電気・水道・ガスの手続き
ひとつずつ見ていきましょう。
1〜4.役所関連の手続き
引越しで別の市区町村に移る場合は、現住所の役所で転出届を提出し、「転出証明書」を発行してもらう必要があります。
この証明書は、新住所の役所で「転入届」を出す際に必要になるため、紛失しないよう保管しましょう。
転出届の提出期限は、引越しの14日前から当日までです。手続きは窓口のほか、自治体によってはオンラインや郵送でも可能な場合があります。
なお、同じ市区町村内での引越しなら「転居届」を提出するだけでOKです。引越し後14日以内に手続きを済ませましょう。
2. 国民健康保険の手続き
国民健康保険に加入している人は、引越しに伴い住所変更の手続きが必要です。
別の市区町村に引越す場合は、現住所の役所で「資格喪失届」を提出し、転入先で新たに加入手続きを行います。
手続きには、国民健康保険証・本人確認書類・マイナンバーの分かるもの・印鑑などが必要です。
引越し後は、転入日から14日以内に手続きを済ませる必要があるため、スケジュールを確認しておきましょう。
同じ市区町村内での引越しの場合は、役所で住所変更の手続きを行うだけで保険証をそのまま使用できます。
3. 印鑑登録の廃止
市外へ引越す場合、現在の自治体で登録している印鑑登録は自動的に廃止されます。引越し後、新しい住所地の役所で改めて登録が必要になります。
手続きの際には、印鑑登録証(印鑑登録カード)を持参し、役所の窓口で廃止手続きを行います。
なお、同じ市区町村内での引越しであれば、印鑑登録はそのまま引き継がれるため、住所変更の手続きをすれば問題ありません。
4. 児童手当・各種医療制度の手続き
児童手当を受給している場合、引越しに伴い「児童手当受給事由消滅届」を提出し、新住所の役所で再申請が必要です。
新居の役所で「児童手当認定請求書」を提出しなければならず、手続きを忘れると受給が途切れてしまう可能性があるので注意しましょう。
また、介護保険や各種医療費助成制度(乳幼児医療費助成、高齢者医療制度など)も、市区町村ごとに制度が異なるため、新住所の役所での手続きが必要になります。
該当する項目について早めに確認し、スムーズに手続きを進めておきましょう。
5. 火災保険・地震保険の契約住所変更
管理会社指定の火災保険に加入している場合、新居の契約時に再度加入が必要になることが多いため、確認しておくと安心です。
保険会社によっては、引越しに伴い保険料の変更や返金が発生することもあります。契約内容を事前にチェックし、必要なら保険代理店に問い合わせておきましょう。
6. 携帯電話の住所変更
手続きは携帯キャリアの店舗やオンラインサービスで簡単に行えるため、早めに済ませておくと安心です。
また、住所変更と同時に、新居のエリアでの通信状況を確認しておくことも重要です。
特に、電波が入りにくい場所では、オプションでWi-Fiルーターを利用するなどの対策が必要になることがあります。
7. 新聞の住所変更
新聞社の公式サイトやカスタマーサービスに連絡し、新しい住所への配達開始日を設定します。
また、地域によっては販売店が異なるため、継続が難しい場合があります。その場合は、一度解約して新居で改めて契約を結ぶ必要があります。
引越し後もスムーズに新聞を受け取るために、早めに手続きを行いましょう。
8. 電気・水道・ガスの手続き
まず、現在の契約会社に連絡し、停止の手続きを進めましょう。
ガスの停止作業は立ち会いが必要なケースが多いため、スケジュールを確認しておきます。
また、新居の契約を忘れると、引越し後すぐに電気や水道が使えないことがあります。
特にガスの開栓には、作業員の立ち会いが必要な場合が多いため、引越し当日に合わせて予約しておくことが重要です。
現在の契約プランや新居の設備に応じて、お得な料金プランへ変更するのもおすすめです。
電力会社の自由化により、複数のプランから選べるので、新居に適した契約内容を検討してみましょう。
引越し1週間前にやること【チェックリスト5項目】
荷造りを中心に準備を進めましょう
1.郵便物の転送手続き
2.日用品の荷造り
3.パソコンのバックアップ
4.ご近所への挨拶
5.挨拶品の準備
それぞれ詳しく解説します。
1. 郵便物の転送手続き
手続き方法は以下の2つです。
●郵便局の窓口で「転居届」を提出
●オンライン(e転居)で申請
手続き後、転送が開始されるまでに1週間ほどかかることがあるため、遅くとも引越しの1週間前には申請しておきましょう。
また、郵便物だけでなく、定期購読している雑誌やネット通販の登録住所も忘れずに変更しておくと、スムーズに新居で受け取れます。
2. 日用品の荷造り
食器類やタオル、衣類は最低限の使うものだけを残し、ほかは早めに梱包します。
掃除用具やティッシュ、ゴミ袋などは、引越し当日まで使うことが多いため、すぐ取り出せる場所にまとめておくと便利です。
また、当日使うシャンプーや歯ブラシ、化粧品、着替えなどを「当日持ち歩き用バッグ」にまとめておくと、引越し後すぐに生活を始められます。
3. パソコンのバックアップ
また、インターネットの契約変更により、一時的にネットが使えなくなる場合があるため、必要なデータはオフラインでもアクセスできるようにしておくのがおすすめです。
パソコン本体の梱包は慎重に行いましょう。
輸送中の衝撃を防ぐため、クッション材でしっかり保護し、できるだけ自分で持ち運ぶのがおすすめです。
4. ご近所への挨拶
また、新居でのご近所付き合いをスムーズにするため、引越し後1週間以内に新居の隣人にも挨拶をすると良いでしょう。
5. 挨拶品の準備
●タオル
●洗剤
●お菓子
一般的な価格の目安は500~1,000円程度です。あまり高価なものは、かえって相手に気を遣わせるため、避けたほうが無難でしょう。
また、新居のご近所への挨拶品も一緒に準備しておくと、引越し後すぐに挨拶を済ませることができます。
引越し前日にやること【チェックリスト3項目】
注意が必要な家電製品の引越し準備をしましょう
1.冷蔵庫の中身の始末
2.洗濯機の水抜き
3.最終確認
それぞれ解説します。
1. 冷蔵庫の中身の始末
なぜなら、霜がついている場合、完全に解けるまで数時間かかってしまうからです。
また、製氷機の水抜きや、内部の水分を拭き取る作業も忘れずに。
電源を抜いた後もドアを開けたままにしておくと、カビや臭いの発生を防げます。
引越し当日はすぐに電源を入れず、設置後3~5時間ほど待ってから電源を入れるようにしましょう。
2. 洗濯機の水抜き
1.空回しで脱水運転を行う:内部の水分をできるだけ取り除く
2.給水ホースや排水ホースを外す:残っている水をしっかり抜く
3.洗濯機のドラム部分が動かないように、購入時の固定ボルトがあれば装着
固定ボルトを紛失している場合は、家電量販店などで代替品を購入するか、引越し業者にあらかじめ相談しておきましょう。
3. 最終確認
また、当日持ち歩く荷物(貴重品・重要書類・スマホの充電器・常備薬・着替えなど)をまとめ、すぐに取り出せるよう準備しておくと安心です。
引越し業者に依頼する場合、作業開始時間や連絡先を再確認し、スムーズに作業が進むよう備えましょう。
これらを事前にチェックしておくことで、引越し当日に慌てることなく、余裕を持って作業を進めることができます。
引越し当日にやること【チェックリスト6項目】
何かと慌ただしい当日もチェックリストがあれば安心です
いよいよ引越し当日、あと一息です
1.旧居の掃除・ごみ処理
2.電気のブレーカーを下げる
3.水道・ガスの元栓を閉める
4.新居の電気・水道・ガスの開始確認
5.目に付く傷や汚れの撮影
6.荷物の確認
1. 旧居の掃除・ごみ処理
退去時のトラブルを防ぐため、床や水回りはできるだけきれいにしておきましょう。
また、引越しに伴って出たゴミや不要品は、自治体のルールに従って処分しましょう。
粗大ごみの回収は予約が必要な場合が多いため、事前に手続きを済ませておくことが大切です。
最後に、すべての荷物を運び出した後、忘れ物がないか最終確認をしましょう。
クローゼットやキッチンの収納、エアコンのリモコンなど、見落としがちな場所も忘れずチェックしてくださいね。
2. 電気のブレーカーを下げる
ブレーカーを上げたままだと、電気代が請求され続ける可能性があるため注意が必要です。
電力会社には事前に停止を連絡し、最終の使用量を確認して精算します。
また、新居の電気をすぐに使えるようにするためには、契約の開始手続きを済ませておくことが重要です。
ブレーカーを上げればすぐに使える場合もありますが、一部の契約では使用開始の申請が必要なケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
3. 水道・ガスの元栓を閉める
水道は基本的に閉めるだけで問題ありませんが、ガスは閉栓作業に立ち会いが必要な場合があります。
ガス会社に連絡し、閉栓日を調整しましょう。オートロックの物件や特殊な設備がある場合は、管理会社とも確認が必要です。
4. 新居の電気・水道・ガスの開始確認
電気はブレーカーを上げるだけで使用できる場合が多いですが、契約によっては事前申請が必要なケースもあります。
水道は元栓が閉まっている場合は、開けて確認してください。
ガスは開栓作業に立ち会いが必要なことが多いため、事前に予約を済ませておきましょう。
作業員が来たら、給湯器やガスコンロが正常に動作するかチェックし、問題があればすぐに相談してください。
これらの手続きをスムーズに進めることで、新居で快適に生活をスタートできます。
5. 目に付く傷や汚れの撮影
壁や床の傷、設備の不具合を記録しておくと、退去時のトラブルを防げます。撮影日が分かるようにしておくと、証拠として非常に有効です。
もし大きな不具合があれば、すぐに管理会社や大家に報告し、修理の対応を依頼しましょう。
6. 荷物の確認
搬入後すぐに破損や紛失を確認し、問題があれば業者に伝えましょう。
後からの請求だと補償対象外になることがあるため、当日中に確認するのが理想です。
また、ダンボールには中身を記載しておくと、必要な荷物をスムーズに取り出せます。引越し後の片付けが楽になるよう、整理しながら荷解きを進めましょう。
引越し後にやること【チェックリスト13項目】
手早くすませて新生活を万全に始めましょう
1.転入届/転居届の提出
2.国民年金・国民健康保険の加入手続き
3.児童手当・各種医療制度の手続き
4.住民票の交付
5.マイナンバーの住所変更
6.印鑑登録の手続き
7.転入先の学校への手続き
8.運転免許証の住所変更
9.車庫証明の取得
10.自動車の登録変更
11.銀行・郵便局口座の住所変更
12.クレジットカード・各種保険の住所変更
13.ペットの登録住所変更・パスポートの住所変更
1〜7.役所関連の手続き
引越し後、新しい市区町村に住む場合は「転入届」、同じ市区町村内での引越しなら「転居届」を役所に提出します。
手続きは引越し後14日以内に行いましょう。期限を過ぎると罰則の対象になることもあります。
手続きに必要なものは、身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)、転出証明書(市区町村をまたぐ場合)、印鑑などです。
転入届を出すと同時に、住民票の写しを取得しておくと、その他の住所変更手続きがスムーズに進みます。
2. 国民年金・国民健康保険の加入手続き
引越し後、国民健康保険と国民年金の住所変更手続きを行います。
国民健康保険の場合、新居の市区町村役場で「加入手続き」を行い、保険証を発行してもらいます。
また、国民年金に加入している人は、役所で住所変更手続きをし、必要な場合は納付書の送付先も変更しましょう。
会社員の健康保険は勤務先で手続きするため、担当部署に確認しましょう。
3. 児童手当・各種医療制度の手続き
児童手当を受給している場合、引越し後の市区町村役場で「児童手当認定請求書」を提出する必要があります。
手続きを忘れると、支給が一時停止されることもあるので注意しましょう。
また、乳幼児医療費助成制度や高齢者医療制度なども、市区町村ごとに制度が異なるため、新居の役所で手続きが必要です。
介護保険の適用対象者も、新しい自治体での登録を行う必要があるため、早めに確認しておきましょう。
4. 住民票の交付
「住民票」は銀行や各種契約の住所変更手続きに必要になることが多いため、転入届を提出した後、役所で取得しておきましょう。
マイナンバーカードがあれば、コンビニで住民票を発行できる自治体もあります。
また、住民票の「世帯主変更」や「続柄の訂正」などが必要な場合は、転入届の提出時に併せて手続きを行うとスムーズです。
5. マイナンバーの住所変更
引越し後、マイナンバーカードの住所変更を役所で行います。住所変更をすると、カード裏面に新住所が記載されます。 また、カードと一緒に「マイナポータル」のログイン情報(暗証番号)も変更になるため、手続き時に確認しておきましょう。
手続きを行わないと、公的な身分証明書としての利用が制限されることがあるため、忘れずに変更を済ませることが大切です。
6. 印鑑登録の手続き
引越しに伴い、前住所の印鑑登録は自動的に廃止されるため、新しい市区町村で改めて印鑑登録を行う必要があります。 役所の窓口で登録を行い、「印鑑登録証(印鑑カード)」を発行してもらいましょう。手続きには、登録する実印・身分証明書・マイナンバーカード(または住民票)などが必要です。
ローン契約や不動産購入で実印が必要になることが多いため、早めに手続きしましょう。
7. 転入先の学校への手続き
引越し後、転校手続きを進めるため、新しい学校に必要書類を提出しましょう。
提出書類には、前の学校で発行された「在学証明書」「教科書給与証明書」などがあります。これらを新居の学校に提出し、転入手続きを行います。
また、通学路や学校設備を確認し、お子様が学校に慣れるようサポートしてあげてください。
8〜10.運転免許や自動車に関する手続き
運転免許証の住所変更は、新居を管轄する警察署または運転免許センターで行えます。
手続きには、新住所を確認できる住民票(またはマイナンバーカード)、印鑑、運転免許証が必要です。
また、自動車を所有している場合、車庫証明や車両登録の変更も必要です。
9. 車庫証明の取得
自動車を所有している場合、引越し後に新しい駐車場の車庫証明を取得する必要があります。
最寄りの警察署で手続きを行いましょう。
交付まで数日かかるため、早めに申請しましょう。
また、駐車場の契約書や車検証のコピーなど、必要な書類を事前に確認しておくとスムーズです。
10. 自動車の登録変更
車の所有者は、引越し後に管轄の運輸支局で住所変更手続きを行う必要があります。
手続きには、住民票・車検証・印鑑(認印可)・自動車保管場所証明書(車庫証明)などが必要です。
変更しないと自動車税の通知が届かないこともあるため、15日以内に手続きしましょう。
11〜12.銀行・郵便局口座やクレジットーカード・保険関連の手続き
銀行や郵便局の口座を利用している場合、住所変更の手続きを行いましょう。
多くの銀行では、インターネットバンキングやATMで住所変更が可能ですが、郵便局の場合は窓口での手続きが必要なことがあります。
住所変更しないと重要な書類が旧住所に届くため、早めに手続きしましょう。
12. クレジットカード・各種保険の住所変更
クレジットカードや生命保険・医療保険の住所変更も忘れずに行いましょう。
住所が変更されていないと、請求書や重要書類が旧住所に送られてしまう可能性があります。
多くの手続きはネットや電話で簡単にできるので、事前に公式サイトで確認しましょう。
13. ペットの登録住所変更・パスポートの住所変更
パスポートの住所変更は義務ではありませんが、本籍変更時は修正が必要です。
まとめ:引越しのチェックリストを用意して、スムーズに新生活をスタートさせよう
やること盛りだくさんの引越しは計画性が重要です
特に、住所変更やライフラインの手続きは早めに済ませ、当日は荷物や設備を確認しましょう。
快適な新生活を始めるためにも、各ステップを計画的にこなしていきましょう。
また、不安なことや疑問がある場合は、プロの引越し業者に相談するのも一つの方法です。
アップル引越センターなら、24時間365日いつでもネットで引越し予約ができ、引越し準備の手間・時間を最小限に抑えられます。
まずはWEBページにアクセスしてみてください。
関連する引越し情報コラム
【新社会人必見】初めての一人暮らし引越し失敗談8選!1年で後悔しない部屋選びと...
2026.02.02
引越しの後悔は、物件選びから入居後の生活まで、さまざまな場面で起こります。 特に初めての引越しでは、費用の安さだけで業者を選んだり、手続きの...
新社会人の引越しでやることを時系列で解説!入社から逆算した失敗しないスケジュ...
2026.02.02
4月の入社を控えた新卒生にとって、実家や学生寮から初めての一人暮らしへ移るケースが一般的です。まず確認すべきは、勤務地へのアクセスです。 新...
【新社会人の引越し】費用・予算の相場は?初期費用を抑える完全ガイド
2025.12.28
春から新社会人としての生活が始まる皆様、おめでとうございます。「引越しにどれくらい費用がかかるのか分からない」「貯金が足りるか不安」と感じて...
【3月は損?】新社会人の引越し時期はいつがベスト?失敗しないスケジュールと準備...
2025.12.28
配属先が早期に決定しているなら、1月から2月上旬が最もおすすめの時期です。 3月に入ると引越し料金は急激に上がりますが、この時期なら通常期の...
転勤による引越しは何から準備する?間に合わないを防ぐ方法を解説
2025.12.03
転勤が決まった直後の初動が、その後の引越しの成否を分けます。特に繁忙期(3月〜4月)と重なる場合、1日の遅れが命取りになることも。 まず最初...
【25選】引越しの失敗談をプロが解説!後悔しないための対策も紹介
2025.12.03
「安さだけ」で業者を選んでしまい、当日の作業品質が悪かったり、追加料金を請求されたりするケースが多く見られます。見積もりは必ず複数社から取り...