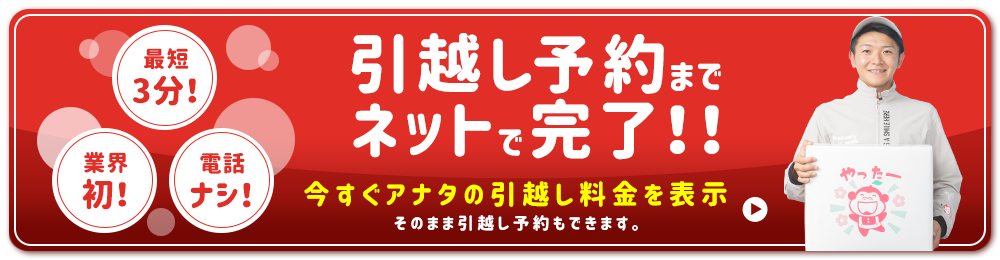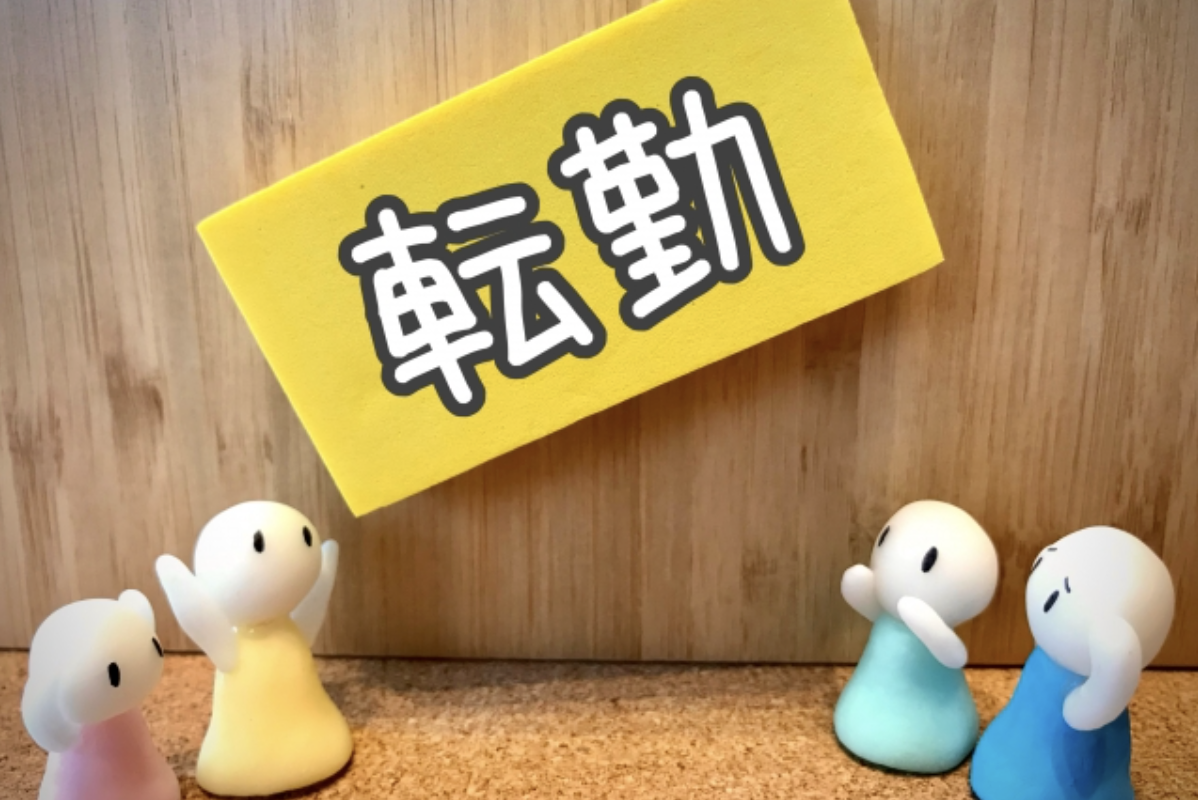【これだけでOK】引越しの荷造り・梱包を効率的に進める8つのコツと準備すべきものを解説

このページの目次
どこから始める?引越しの荷造り・梱包を効率よく進めるコツ8つ
コツ①:荷造りすべき場所をグループに分ける
そのためには、荷物を部屋ごとやエリア別にグループ分けするのが効果的です。
例えば、「リビング」「キッチン」「トイレ」など大まかに分けたあと、さらに「リビング1(テレビ・ソファ)」「リビング2(本棚・観葉植物)」と細分化しておくと、作業の全体像がつかみやすくなります。
簡単な間取り図を作るのも効果的です。
荷造りは3〜4週間前から、シーズンオフや使用頻度の低いものから始めましょう。
こうした準備を段階的に進めることで、膨大に思える荷物も意外と少なく感じられ、気持ちもラクになります。
コツ②:引越しまで使わないものから先に梱包する
・季節外れの服
・来客用の食器
・使っていない本や趣味のグッズ など
梱包の最初は、今すぐ必要ないものから手をつけましょう。こうしたアイテムは生活への支障が少ないため、早い段階で箱詰めできます。
その一方で、引越し当日まで使用するような、生活に必要なものは最後に梱包するようにしましょう。
荷物の優先順位を意識しながら進めることが、普段の生活を乱さずに引越し準備を進めるカギです。
コツ③:使う予定のあるものは段ボールに封をしない
歯ブラシやシャンプー、タオル、最低限の調理器具など、日常的に使うアイテムをすぐに取り出せる状態にしておくことで、引越し当日まで快適に過ごせます。
開封したままの段ボールは、引越し当日の朝に封をするのが理想です。
これにより、荷造りの途中で必要なものを探し回る手間がなくなり、ストレスなく引越し準備を進められます。
コツ④:段ボールのサイズ選びを気をつける
段ボールは荷物に合った大きさを選ぶことで運搬がラクになり、破損も防げます。
軽くてかさばるもの(衣類・布団など)は大きめの段ボールに入れると、一度にまとめて運べます。
ただし、本や食器類など重くなりやすいものは小さめの段ボールに分けるのが基本です。
また、大きな箱に詰めると重量オーバーになることも。持ち運びが大変になるだけでなく、底が抜けるリスクもあります。
小さすぎる段ボールは荷物が入りきらず、箱の数が増える原因になるので注意しましょう。
コツ⑤:新居で不要なものは処分する
新居に持って行く必要のないものを事前に処分すれば、荷物量が減り、引越し費用や作業時間の削減にもつながります。
まずは、使っていない家電や家具、着なくなった衣類、本・雑誌などをリストアップしてみましょう。
処分方法としては、以下の方法が一般的です。
・自治体の粗大ごみ回収を利用する
・リサイクルショップやフリマアプリで売却する
・不用品回収業者に依頼する など
家電や家具は付属品が揃っていると高く売れることもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
引越し業者によっては「不用品の引き取りサービス」を提供している場合もあります。
ただし、料金がかかることもあるため、事前に業者へ確認し、コストを比較検討するのがおすすめです。
引越し料金を安くしたい方は、こちらの記事もご覧ください。
【詳細はこちら】 https://apple-hikkoshi.jp/archives/554/
コツ⑥:遅くても1〜2週間前から準備を始める
直前になって慌てると、荷造りだけでなく、各種手続きや掃除にも手が回らなくなり、引越し当日にトラブルが発生しやすくなります。
この時期にやるべきこととしては、おもに以下のような作業が挙げられます。
・役所での転出届の手続き
・電気・水道・ガス・インターネットの解約・移転手続き
・賃貸物件の退去連絡 など
引っ越しに関する作業内容について詳しく知りたい方は、チェックリストを活用しましょう。
【詳細はこちら】 https://apple-hikkoshi.jp/archives/2219/
また、旧居の掃除スケジュールを立てておくことで、スムーズに退去できるようになります。
コツ⑦:新居ですぐに必要なものは段ボールに印をつける
スムーズに生活をスタートするために「最優先ボックス」を作り、目立つ印をつけておきましょう。
最優先ボックスに梱包するべきもの
・歯ブラシ
・タオル
・洗面用具
・最低限の調理器具
・携帯やパソコンの充電器
・Wi-Fiルーター
・仕事や学校で使う書類 など
これらは新生活スタート後、すぐに必要になる可能性が高いです。
そのため、1つの段ボールにまとめて「最優先」と記載し、色付きテープでマーキングしておくと荷解きの際に迷わず取り出せます。
コツ⑧:引越し後の片付けを効率的にするポイントを知る
各段ボールに「部屋名」と「内容物」を明記し、新居で該当する部屋へ直接運び込むことで、不要な移動を減らせます。
また、開封の優先順位を決めておくと、さらに効率的です。
まずは最優先ボックスを開け、次に日常生活に必要な衣類やキッチン用品を取り出し、最後に趣味のものや装飾品などの使用頻度が低いものを開封します。
梱包時に「用途別・種類別」に整理しておくと、新居での整理整頓がスムーズになり、無駄な手間を省けます。
【無駄買い防止】引越し梱包に本当に必要な道具と意外と不要なもの
必要な道具(事前に準備しておくべきもの)
必要な道具をそろえておけば、作業がスムーズに進み、荷物の破損を防げます。
また、意外と不要なものを買いすぎてしまうケースもあるため、無駄な出費を抑える工夫も大切です。
ここでは、荷造りに必要な道具と意外といらないものを紹介します。
必要な梱包資材は以下のとおりです。
・段ボール:一人暮らしなら約20個、家族なら約45個が目安
・ガムテープ:布タイプが丈夫でおすすめ。色違いを使い分けると便利(例:「新居ですぐに使う荷物=赤」「後回しの荷物=茶色」)
・新聞紙・緩衝材(プチプチ):ワレモノの保護に必須
・ビニール紐:本や雑誌、傘などをまとめるのに使用
・ビニールテープ・セロハンテープ:緩衝材の固定や細かいアイテムの整理に使用
工具・小物類としては、以下を用意しておくと良いでしょう。
・ハサミ・カッター:テープや緩衝材をカットするのに使用
・マジック(油性ペン):段ボールの天面・側面に中身を記入することで、荷ほどきをスムーズに
・工具類(ドライバー・六角レンチなど):組み立て家具の解体・組み立てに必要
・軍手:荷物運搬時の滑り止めやケガ防止に役立つ
・養生テープ:家具の引き出しや扉の仮止めに最適
・割れものシール:ワレモノを入れた段ボールに貼ることで、作業員の注意を促せる(赤ペンで「ワレモノ注意」と書くのも効果的)
その他にも、ゴミ袋(荷造り中に出るゴミの処理に必須)や、ジップロック・ビニール袋(小物や液体がこぼれる可能性のあるものをまとめる)などもあると便利です。
意外と不要なもの
・大量の緩衝材 → 新聞紙や衣類で代用可能
・高価な専用梱包ボックス → 通常の段ボールで十分な場合が多い
・過剰な工具類 → 基本的な工具以外は、必要になったときに購入or借りる方が効率的
・大量の梱包用紐 → ガムテープで代用可能
・新品の掃除用具 → 引越し前の掃除には、既存の掃除用具で十分
あって困りはしませんが、追加でわざわざ購入する必要はありません。
失敗しない引越し計画!家族構成別の最適な荷造りスケジュール
単身者は2〜3週間前からの準備が理想
単身者の場合、「2〜3日で終わるだろう」と甘く見ていると、引越し直前にバタバタする原因になります。
日常生活や仕事に追われる中での荷造りは、思った以上に進みません。
そのため、2〜3週間前から少しずつ始めるのが理想です。計画的に進めることで、引越し当日に慌てることなくスムーズに終えられます。
また、荷造り以外にも住所変更などの手続きや掃除など、やるべきことが多くあります。「退去時の掃除のやり方がわからない」という方は、以下の記事も参考にしてみてください。
【詳細はこちら】 https://apple-hikkoshi.jp/archives/629/
引越し作業を無理なく進めるためにも、できるだけ早く準備に取りかかるようにしましょう。
家族の引越しは1ヵ月前から計画的に
そのため、1ヵ月前から計画的に荷造りを始めるのがおすすめです。
例えば子どもの学用品や季節用品、思い出の品など、家族構成によって整理するべきものも増えるため、短期間で終わらせるのは難しいです。
計画的に取り組むことで、ストレスを軽減でき、作業もスムーズに進みます。
また、どうしても時間がないという場合には、短期間で引越しを完了させる方法もあります。
引越し当日にバタつかないためにも、家族の引越しはとくに早めの準備が肝心です。
荷造り・梱包用の段ボールは買うべきか?業者にもらえる?
多くの大手引越し業者は無料で段ボールを提供してくれる

実際、多くの大手引越し業者では、契約者向けに無料で段ボールを提供しています。 ここでは無料提供の段ボール事情と自分で用意する場合の方法について解説します。
大手引越し業者の多くは、契約者向けに一定枚数の段ボールを無料で提供しています。
無料提供の条件としては、基本的にその業者と契約することが前提となっていますが、業者ごとに段ボール枚数や提供条件が異なる点には注意しましょう。
また、無料で提供される枚数では足りないケースもあるため、追加で購入が必要になることもあります。
業者によっては、有料で追加購入できる場合や、オプションサービスとして梱包資材をセットで提供しているところもあるため、契約時に確認しておきましょう。
無料で手に入る?自分で段ボールを用意する方法
ただし、適当に入手した段ボールを使うと、底抜けなどのトラブルが発生することがあります。
そのため、基本的には自分での用意はおすすめしていません。引越し業者の提供する段ボールを利用しましょう。
個人で段ボールを入手する際は、ホームセンターや通販サイトで購入できます。
注意点は以下のとおりです。
・古い段ボールは避ける:湿気や傷みがあると強度が落ち、底抜けのリスクがあるため、新品を選ぶのがベスト
・適切なサイズを選ぶ:大きすぎると持ち運びが大変になり、小さすぎると荷物が収まりきらないため、荷物に合ったサイズを選ぶことが重要
・強度をチェックする:本や食器など重い荷物を入れる場合は、厚みのある頑丈な段ボールを選ぶ
さらに、段ボールの入手方法について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
【詳細はこちら】 https://apple-hikkoshi.jp/archives/1166/
荷物別!引越しの荷造り・梱包方法【ジャンル別に解説】
割れ物【茶碗・グラス/コップ・平皿・包丁など】
引越しで最も注意が必要なのが割れ物の梱包です。
茶碗やグラス、平皿などは輸送中の衝撃で簡単に割れてしまうため、適切な梱包を行うことが大切です。
また、包丁のような刃物類は安全に運ぶ工夫が必要になります。
・茶碗・小鉢・丼の梱包
茶碗や小鉢は、1つずつ新聞紙や緩衝材で包み、重ねずに詰めるのが基本です。重ねる場合は、小さいものから順にひっくり返して積み、間に新聞紙を挟んで衝撃を吸収しましょう。箱の中で動かないよう、すき間には丸めた新聞紙を詰めるのがポイントです。
・グラス・コップの梱包
グラスやコップは横に寝かせると割れやすいため、伏せた状態で立てて梱包します。特にワイングラスは脚の部分が壊れやすいので、厚めの緩衝材で包み、立てた状態で詰めるのが理想的です。また、円錐形のグラスは互い違いにすると、箱の中で安定します。
・平皿の梱包
平皿は1枚ずつ新聞紙で包むか、じゃばら折りにした新聞紙の間に挟んで保護します。複数枚まとめて包む場合は、養生テープで固定するとズレにくくなります。箱の中では平置きせず、縦に立てて並べると衝撃を分散できるため、破損のリスクを減らせます。
・包丁などの刃物の梱包
包丁は刃がむき出しにならないよう、厚紙や段ボールで刀身を覆い、ガムテープでしっかり固定します。さらに、新聞紙や布で包むと安全です。「包丁」「刃物注意」などと書いておくと、荷解き時の事故を防げます。
割れ物の梱包は、慎重に行うことが大切です。段ボールには「ワレモノ注意」と目立つように書き、運搬時に慎重に扱ってもらうよう配慮しましょう。
キッチン用品【調理器具・調味料】
・調理器具の梱包
フライパンや鍋は重ねて梱包すると省スペースになります。取っ手が外せるものは外してまとめると、よりコンパクトに収納できます。フタと本体は別々に包み、すき間には新聞紙や布を詰めると動かずに済みます。
・調味料の梱包
液体調味料はこぼれやすいため、しっかり蓋を閉めたうえで、ビニール袋に入れて密封するのが基本です。瓶や缶など重い調味料は、小さめの段ボールに詰めることで、運搬時の負担を軽減できます。
調味料の梱包・荷造りについてはこちらの記事でも詳しく解説しているので、あわせてチェックしておきましょう。
【詳細はこちら】 https://apple-hikkoshi.jp/archives/1170/
衣類
・ハンガーにかかった衣類
ハンガーボックスを使えば、服をハンガーごと移動でき、シワがつきにくくなります。スーツやワイシャツ、コートなどは特にこの方法がおすすめです。専用のボックスがない場合は、大きなゴミ袋を利用して服を包むと代用できます。
・衣装ケースに入った衣類
衣装ケースの中身は取り出さず、そのまま運ぶのが手間がかからず便利です。ただし、フタや引き出しが開かないように養生テープで固定しておくと、輸送中のトラブルを防げます。
・その他の衣類
シーズンごとや種類別に分けて梱包すると、新居での荷解きがスムーズです。整理ダンスの中身は、引き出しごとに箱に詰めると、移動後の片付けが楽になります。
衣類は圧縮袋を活用するとかさばらず、コンパクトに収納できます。
ただし、長期間圧縮するとシワが残るため、引越し後は早めに開封するのが理想的です。
家具【大型家具・組み立て式家具】
・大型家具の梱包
基本的に大型家具は解体せず、そのまま運びましょう。ただし、扉や引き出しが開かないように養生テープで固定し、輸送中の事故を防ぐことが大切です。傷がつきやすい部分は、毛布や緩衝材で保護すると安心です。
・組み立て家具の梱包
可能であれば解体し、部品ごとにまとめておくと運びやすくなります。ネジや金具はビニール袋に入れ、ラベルを貼っておくと、組み立て時に迷わずに済みます。組立説明書も一緒に保管しておくと、スムーズに再組み立てできます。
家具は大きくて扱いが難しいため、無理に1人で運ぼうとせず、必要なら引越し業者に依頼するのも一つの方法です。
家電【テレビ・DVDレコーダー・冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・パソコン・小型家電】
・テレビ・DVDレコーダーの梱包
購入時の箱と緩衝材が残っていれば、それを使うのが最も安全です。ない場合は、画面を保護するために毛布や段ボールをあてがい、さらに気泡緩衝材(プチプチ)で包みましょう。コード類はまとめてビニール袋に入れ、テレビ本体に貼り付けておくと、荷解きの際にすぐに接続できます。
・冷蔵庫の梱包
冷蔵庫は引越しの数日前から電源を抜き、庫内の霜取りと乾燥を行っておく必要があります。棚板や食品をすべて取り出し、ドアが開かないようにテープで固定します。庫内に水分が残っていると、輸送中に漏れて他の荷物を濡らす恐れがあるため、しっかり乾燥させましょう。
・電子レンジの梱包
電子レンジは内部のターンテーブルや付属品を取り出し、それぞれ別に包みます。本体は気泡緩衝材でしっかり包み、「天地無用」と書いて上下逆さまにされないように注意を促しましょう。重ねて置かれると壊れる可能性があるため、目立つ位置に注意書きを貼るのがおすすめです。
・洗濯機の梱包
洗濯機は使用後に排水ホースの水を抜き、内部を乾燥させてから梱包します。ホースや電源コードは本体に固定し、可能であれば輸送用の固定ボルトを取り付けて内部のドラムを保護します。重くて扱いにくいため、運搬は必ず複数人で行いましょう。
・パソコン・小型家電の梱包
パソコンはデータのバックアップを事前に行っておくと安心です。本体と周辺機器をそれぞれ緩衝材で包み、段ボールの中で動かないよう詰め物をします。コード類はまとめてラベリングし、セットにして管理すると、新居での再設置がスムーズになります。ドライヤーや電気ケトルなどの小型家電も1台ずつ丁寧に包みましょう
家電製品は壊れると修理費がかかることが多いため、丁寧かつ慎重に梱包することが大切です。特に大型家電や精密機器は、可能であればプロの業者に任せることも検討しましょう。
お風呂用品
そのため、液体類は蓋をしっかり締めたうえでビニール袋に入れ、袋の口も結んでおくと安心です。ボトル類は立てて詰めるのが理想です。
バスタオルや洗面器、椅子などは同じ種類でまとめ、タオルは緩衝材としても活用しましょう。お風呂掃除用のブラシなども、乾かしてから忘れずに梱包してください。
最後に使うものが多いため、お風呂用品は引越し当日にまとめて詰めるとスムーズです。清潔な状態で新居に運ぶためにも、事前準備がカギになります。
本・書類
本はサイズをそろえて横向きに入れると安定し、すき間には新聞紙やタオルを詰めて動きを防ぎましょう。これにより、運搬中の破損リスクも軽減できます。
書類はクリアファイルにまとめ、重要なものはすぐに取り出せる位置に収納するのがおすすめです。引越し中に紛失すると再発行が面倒なため、最優先で管理しましょう。
不要な雑誌や古い書類はこの機会に整理するのが◎。荷物が減り、引越し後の収納もスムーズになります。重くなりがちな本や書類こそ、工夫次第で安全かつ効率的に運べます。
引越し用段ボールの組み立て方の3つのコツ
コツ①:底を十字にテープで補強する
段ボールの底は荷物の重さが集中する部分です。そのため、強度を高めるための補強が欠かせません。
基本の手順は、まず短いフタを内側に折り、次に長いフタを重ねて閉じます。その上からガムテープを「十字」に貼ることで、中心部の強度をしっかり確保できます。
さらに補強を強化したい場合は、フタの角に追加のテープを貼る「キ貼り」や、斜め方向にもテープを貼る「米字貼り」もおすすめです。
とくに本や食器、家電など重量がある荷物を入れる場合は、こうした補強方法を活用しましょう。
テープは布テープが粘着力・耐久性ともに優れており、重い荷物に適しています。
軽量な荷物用にはOPPテープ(透明テープ)でも問題ありません。
コツ②:歪まないように正確に組み立てる
正しい順序は、短いフタ→長いフタの順に折りたたみます。この順番を守らないとフタに隙間ができ、強度が落ちてしまうんです。
また、テープを貼るときは、均等な力でしっかり押し付けながら貼ると、剥がれにくくなります。
箱が歪んだまま荷物を詰めると、上に積み重ねた際に崩れやすくなります。
複数の箱を重ねて運ぶことを考慮して、丁寧に組み立てることが大切です。
コツ③:適切なサイズ・材質を選ぶ
荷物の重さや大きさに合っていない箱を使うと、持ち運びが不便になるだけでなく、破損や事故の原因になります。
たとえば、本や調味料など重い荷物には小さめ段ボールを、衣類や寝具など軽くてかさばるものは大きい段ボールが向いています。
引越し業者の荷づくりサービスとは?メリット・デメリットを解説
引越し業者の荷造りサービスを使うメリット
そんな人には、引越し業者の荷造りサービスがおすすめです。
最大のメリットは、時間と労力の削減です。仕事や育児で忙しい人、体力に不安がある人でもスムーズに引越し準備を進められます。
また、プロが梱包してくれるため、作業が速く、破損リスクも低いです。食器や家電なども適切に保護して運んでくれます。
引越し当日まで通常の生活を維持できるのも魅力です。
自分で荷造りすると日用品を早めに片づける必要がありますが、業者に任せれば直前まで普段通りに過ごせます。
さらに、段ボールや梱包資材の準備・回収も業者が対応するため、後片付けの手間も省けます。
引越し業者の荷造りサービスを使うデメリット
通常の引越しより料金が高くなり、予算が限られている人には負担になることもあります。
また、スタッフが家の中に入り、私物を扱うためプライバシーが気になるという声も。
大切な書類や見られたくないものは、事前に自分で梱包するのが安心です。
利用するときは事前に口コミや評判を確認し、信頼できる業者を選びましょう。
とはいえ、時間がない人や、体力的に荷造りが難しい人にとっては大きな助けになるサービスです。
予算や状況に応じて、必要な部分だけ依頼するのも一つの方法です。
まとめ
スムーズな引越しは準備で決まる!8つのコツを実践して新生活を最高のスタートに!

使わないものから梱包し、適切なサイズの段ボールを選ぶことで、作業の負担を減らせます。もし時間がなくて荷造りが間に合わない場合は、引越し業者の荷づくりサービスを活用するのも一つの方法です。
アップル引越センターにお問い合わせください!
特に単身世帯向けのお得なプランが充実しており、費用を抑えながらスムーズに新生活をスタートできます。
コストを抑えて安心・快適な引越しをしたい方は、ぜひご相談ください。
関連する引越し情報コラム
【新社会人必見】初めての一人暮らし引越し失敗談8選!1年で後悔しない部屋選びと...
2026.02.02
引越しの後悔は、物件選びから入居後の生活まで、さまざまな場面で起こります。 特に初めての引越しでは、費用の安さだけで業者を選んだり、手続きの...
新社会人の引越しでやることを時系列で解説!入社から逆算した失敗しないスケジュ...
2026.02.02
4月の入社を控えた新卒生にとって、実家や学生寮から初めての一人暮らしへ移るケースが一般的です。まず確認すべきは、勤務地へのアクセスです。 新...
【新社会人の引越し】費用・予算の相場は?初期費用を抑える完全ガイド
2025.12.28
春から新社会人としての生活が始まる皆様、おめでとうございます。「引越しにどれくらい費用がかかるのか分からない」「貯金が足りるか不安」と感じて...
【3月は損?】新社会人の引越し時期はいつがベスト?失敗しないスケジュールと準備...
2025.12.28
配属先が早期に決定しているなら、1月から2月上旬が最もおすすめの時期です。 3月に入ると引越し料金は急激に上がりますが、この時期なら通常期の...
転勤による引越しは何から準備する?間に合わないを防ぐ方法を解説
2025.12.03
転勤が決まった直後の初動が、その後の引越しの成否を分けます。特に繁忙期(3月〜4月)と重なる場合、1日の遅れが命取りになることも。 まず最初...
【25選】引越しの失敗談をプロが解説!後悔しないための対策も紹介
2025.12.03
「安さだけ」で業者を選んでしまい、当日の作業品質が悪かったり、追加料金を請求されたりするケースが多く見られます。見積もりは必ず複数社から取り...